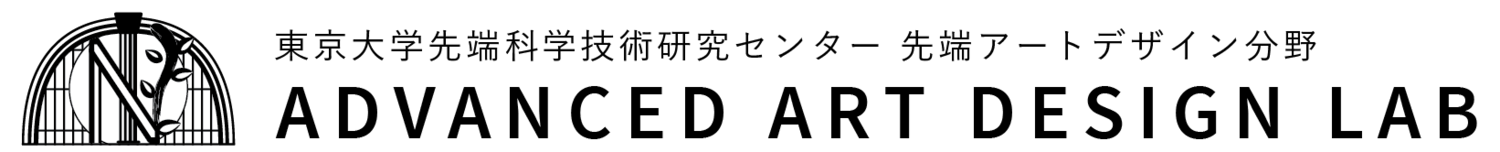高野山会議2024を開催
学校訪問コンサートの様子
============= INFORMATION =============
■2025年大阪・関西万博
高野山会議開会式にて、東大先端研と大阪万博2025のイタリアパビリオンがパートナーシップを結び、2025年7月、大阪万博イタリアパビリオンにて高野山会議エクステンションが行われることが発表されました。
伊藤節特任教授、伊藤志信特任准教授、Rossella Menegazzo 客員准教授
============= REPORT =============
■高野山会議 開催報告
7/10~7/13に世界遺産登録地、高野山にて「高野山会議2024」を開催しました。先端研内外から33名の講師を迎え、多様なプログラムを用意した本会議には、悪天候にも関わらず延べ約1,800名の方が参加され、大変盛況のうちに終了しました。各セッションおよびプログラム担当教員より簡単な報告を以下に記します。
【セッション01】 「WAの芸術とデザイン_継承と変換」
主管:伊藤志信(先端研 特任准教授)
AAD開設当時から継続しているこの議題は、 和のクリエイティビティとサステナビリティの探究をテーマにしています。2024年は継承と変換を付随題目に、輪島、漆の桐本泰一氏、京都、茶筒の開化堂の八木隆裕氏、ガラス造形作家の西中千人氏をゲストに、アート・デザイン側からの震災復興、変わらずに変わっていく事の継承と変換性、リサイクルガラスによるアートの変換と可能性等について、様々な論議が行われました。
【セッション02】 「高野山と宇宙」
主管:吉本英樹(先端研 特任准教授)
このセッションでは、高野山の僧侶・山口文章さん、天文学者・渡部潤一さん、写真家・上田優紀さん、JAXA・大塚成志さんの4名のゲストにご登壇いただき、四者四様それぞれの視点から、宇宙の深い魅力について語って頂きました。全く異なる視点で、広大な宇宙のように幅広い話題を頂いた一方で、宇宙における人間の生・存在という観点で、全員が同じところに着地するような感覚もあり、非常に盛り上がり、刺激的なセッションとなりました。
【セッション03】 「インクルーシブデザイン」
主管:伊藤節(先端研 特任教授)
宇宙や自然と一体化する東洋的な包摂思想の発信地である高野山で、インクルーシブソサエティ実現に向けた議論を行うことは有効である。昨年までは主に身体機能障がい当事者研究者とインクルーシブデザイン・アートの研究者に登壇頂いたが、今年は私と並木重宏氏が進行を務め、感覚機能障がい当事者研究者として著名な福島智氏、松森果林氏、そして企業でインクルーシブデザインを進める資生堂の和久井裕史氏、塩田笑子氏に登壇頂き、感覚障がい当事者の視座と企業デザイナーの視点で議論を展開した。人同士の生のコミュニケーションの重要性が切実に問われ、豊かな会話が実現できれば感覚障がい者も人生の喜びや「美しさ」を感じることができる、ということが確認された。
【セッション04】「次世代育成」悠久の絆を包摂する環境創造[まちづくり]
主管:近藤薫(先端研 特任教授)
昨年に引き続き次世代育成についてのセッションを開催しました。かねてよりアートラボでは次世代育成の重要な要素として「ひとづくり」と「まちづくり」の2つの側面を見出しており、高野山会議2024では「まちづくり」に焦点を当てました。丹生都比売神社の宮司である丹生晃市氏による世界遺産の継承を通じたまちづくり、そして前長久手市長の吉田一平氏によるいつまでも完成しない(完成させない)ゆっくりとしたまちづくりについて、お二人の人生哲学と共に語っていただきました。人の人生では図りきれない悠久のまちづくりの本質的な手掛かりを得られただけでなく、お二人のお人柄もあり、ホッと一息つける朗らかなセッションとなりました。
【セッション05】世界遺産登録20周年記念シンポジウム
「紀伊山地に育まれた精神性と自然から世界につたえること」
主管:神﨑亮平(先端研 シニアリサーチフェロー)
本年2024年は「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されて20周年となる。これを記念して高野山大学黎明館で開催された本シンポジウム(セッション05)には、地域の多くに皆さんにもご参加いただき、岸本周平知事のオープニングトークに始まり、前半は紀伊山地の古来の精神性である“利他のこころ”や“いのちの大切さ”について、弘法大師空海や南方熊楠の視座から(松長潤慶、藤原和博、田村義也)、またこのような精神性を育んできた地元の首長(真砂充敏田辺市長、平野嘉也高野町長)の講演で進んだ。後半のパネルディスカッションでは、このようなこころ・精神性を育んできた紀伊山地が世界遺産登録されたことの意義についてそれぞれの立場から議論された。紛争や戦争、飢餓、環境問題が絶えない世界へこのようなこころ・精神性を世界に発信していくこと、そして次世代に受け継ぎ実践していくことの大切さが会場も一体となり確認された。2025年に開催される大阪・関西万博はそのような場として最適であることも示された。
【セッション06】「ひとはなぜ戦争をするのか?」
統括:杉山正和(先端研 所長・教授)
セッション06では、東京大学が誇る多様な学術領域から第一線の研究者を集め、科学技術が飛躍的に進歩した現代に至っても人類が戦争を止めない理由を多面的に深く議論しました。90年前に出版されたアインシュタインとフロイトの往復書簡「人はなぜ戦争をするのか」を出発点として、ひとを戦争に駆り立てる本質的なメカニズムと戦争の抑止策について、脳神経科学、哲学、政治学、ゲノム人類学、グローバルな宗教学、ジャーナリズムの観点から意見が交わされ、人間と動物の違い、教育の重要性、国家の役割、芸術と戦争の関連性など多岐にわたる論点が抽出されました。しかし、戦争のない社会を実現するための方向性を示すには至っておらず、この深淵かつ重要なテーマに対して議論を継続していく予定です。
=セッション以外のプログラム=
【コンサートシリーズmeets】 主管:近藤薫
高野山で演奏するのが夢だったという、世界に誇る邦人バイオリニスト堀米ゆず子氏に初登場いただき、J.Sバッハの無伴奏パルティータ第2番を、金剛峯寺本坊大広間にてご披露いただきました。バッハの音楽堀米さんの人生が現れた素晴らしい演奏で、特に終曲のシャコンヌは深い感動を呼ぶ名演でした。演奏後のインタビューでは「空海さんと同行二人のようでした」とのお言葉をいただき、無伴奏というたった一人で弾き切る難曲に新たな視点が加えられたように感じました。
【学校コンサート】主管:近藤薫
橋本市と高野町の小中学生向けに、学校コンサートを開催しました。「障がいがあったからこそ生まれた名曲」をテーマに、モーツァルト、ベートーヴェン、シューマン、スメタナの楽曲をお話付きで鑑賞して貰いました。毎年開催している学校コンサートですが、実際にバイオリンを始める生徒が出現するなど、目に見える結果も出つつあります。
【クロージング クラシックコンサート】主管:近藤薫
恒例となったクロージングでのクラシックコンサートは、毎年楽しみにしているというお客さんが増え、高野山内外から多くご来場いただきました。「視点を変える」をテーマに、バッロク時代と米ソ冷戦時代の戦争を扱った曲の比較から始め、コンサート後半ではヴィヴァルディ、早川正昭、ピアソラの四季を並べ、それぞれの視点からの「夏」を演奏しました。図らずとも近藤薫の指揮者デビューとなった本公演は、弦楽合奏団の絶妙なアンサンブルと各曲の独奏者の熱演により、盛況のうちに幕を閉じました。
【先端アート展示】 主管:伊藤志信/吉本英樹
〈Teacaddy〉テーブル、スツール、ミニテーブル
デザイン:伊藤節、伊藤志信 制作:開化堂、協力ː中川木工芸
「イングランディメント」イタリアのアートデザインで使われる手法の1つで、拡大することで、そのものに対する共感性や存在意義、象徴性を表現している。一貫した手づくりで一世紀を過ぎた今も尚、初代からの手法を守り続けてきた、茶筒づくり日本最古の歴史をもつ京都の開化堂、その茶筒の素材と技法を使い、それをファニチャー(テーブル・スツール)にイングランディメントしたアート・デザイン作品である。
〈Rose〉
デザイン:吉本英樹 制作:株式会社箔一、大蔵山スタジオ株式会社、株式会社ブルド
高野山の麓、天野の地にある丹生都比売神社。ここに祀られる丹生都比売大神は弘法大師空海に高野山の地を授けた神様です。ときに重ね合わせて語られる、大日如来と丹生都比売大神。その神仏習合のすがたを表現したいと思い、この作品を創りました。そこに描かれるのは、丹生都比売神社に伝わる、美しい薔薇の紋様です。
—————————————————————————
■吉本英樹
8/19に、東大先端研ENEOSホールにて、東京大学との共催による特別公開レクチャーシリーズ Vol. 6 拡大版「会津本郷焼 x Hideki Yoshimoto / LEXUS x 越前和紙 x Tangent」を開催しました。
オフィシャルサイト:https://www.craft-x-tech.com/
============= CALENDAR 2024 =============
8/18 - 21 高野山青少年会議研修@高野山(対象者のみ)
9/6 駒Ⅱ音楽祭@先端研ENEOSホール(要申込)
(次回以降のスケジュール---11/7, 2025/1/17)